微禄造句
造句与例句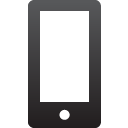 手机版
手机版
- 川島家は30石の微禄であった(後に7石加増)。
- 同心勤務をしながら、微禄を補うために画を志した。
- このほか能勢源五右衛門家には微禄の末家1戸がある。
- 土佐藩士の中でも身分の低い微禄の家柄の息子として生まれた。
- 微禄(150石の小普請組)ながら勝海舟に洋学を学ぶなど向上心が高い。
- 野村はもともと8石3人扶持という微禄の小者に過ぎなかったが、定重は野村の実力を評価して登用した。
- 武士階級も一部処罰されているが、武士の処罰は下級身分の者に限られ、最高でも微禄の旗本しか処罰されていない。
- 孫に当たる与次郎宗吉(菅野金光家(岡山市菅野)の祖と思われる)と清右衛門は後に池田氏(岡山藩)に微禄で仕えた。
- これらは軍制上は小禄?微禄でも大組の扱いであった(もともと大組所属の藩士の子弟、すなわち部屋住み身分であるため)。
- また、分配金の配分では大石は微禄の者に手厚く配分すべきとしたのに対して、大野は石高に応じて配分すべきと主張している。
- 用微禄造句挺难的,這是一个万能造句的方法
- そして、縁あって越前松平家に召抱えられ、禄高500石(のちに650石)の微禄であったが子孫は同家に仕え明治維新を迎える。
- その後、このルーツは、享保年間にも、30石の微禄の分家を分出した後、10石の加増が2回あったと推察され世襲家禄を240石とした。
- 先祖?七左衛門啓道が、故あって慶安元年(1648年)に長岡藩主牧野家に仕え、高野姓に改称して微禄の中級藩士(馬廻り衆)となった。
- 池田光政が藩主をしていた寛文2年(1662年)頃に太郎右衛門の孫である与次郎宗吉と弟の清右衛門の家系は池田氏(岡山藩)に仕官し、微禄で代々仕えた。
- 徳島藩の客将とされていたが、藩主蜂須賀家政の意向により家禄を微禄の100石余に減じ、足利姓から平島姓への改姓を強要し、その権威を落とすため冷遇した。
- しかし北越戦争の事実上の責任者は河井継之助で、彼が新興微禄の家老だったため、高禄譜代の上席家老だった山本帯刀がこれに添えられるかたちで犠牲にされたことは否めなかった。
- 藩士に給付する蔵米については、いわば最低保障が付けられた微禄の藩士を除き、知行100石に対して20俵給付にまで落ち込み、長く20俵台から抜け出せずにいた(一般的には知行100石で40俵)。
- 織田信長に抵抗した三好氏に擁立された家系であるため、織豊期および徳川期にも冷遇され、江戸期以降は阿波徳島藩主?蜂須賀氏の客将として扱われたが、蜂須賀氏は平島公方家に下級藩士並みの微禄しか許さず、後には足利氏の家名を平島氏に改めさせるなど冷遇した。
- 御家人は大都市の江戸に定住していたために常に都市の物価高に悩まされ、また諸藩では御家人と同じ程度の家禄を受けている微禄な藩士たちは給人地と呼ばれる農地を給付され、それを耕す半農生活で家計を支えることができたが、都市部の御家人にはそのような手段も取ることができなかったことが理由としてあげられる。
其他语种
- 微禄的日语:薄禄,微薄的俸禄,沦落,零落
Last modified time: Tue, 12 Aug 2025 00:29:56 GMT
